

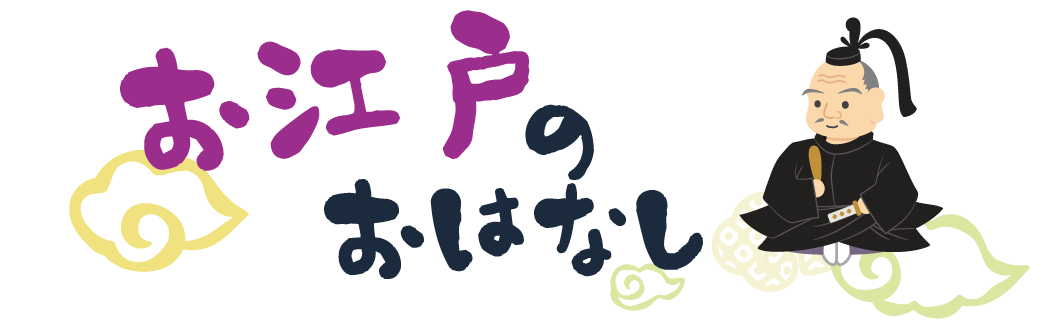
徳川幕府開府から3年後の1606年、ようやく江戸城の大増築を藤堂高虎に命じた徳川家康。図面ができ、施工者も大工頭、今でいうなら大手ゼネコン社長に近い総合職の中井正清に決まりいよいよ普請が始まろうというとき、すでに将軍となっていた徳川秀忠から「江戸城に天守はいらない」という声があがりました。「信長・秀吉の時代は城攻めに備え戦に耐えうるために天守は必要だったが、江戸には高い山も急な崖もないから砦にはならない」と。「今はむしろ統治の便、交通の便を重んじた造りが必要であり天守は無用の長物である」と家康に意見したようです。
結局のところ、全国の大名を動員し大規模工事に従事させることで潜在能力を減殺させ、徳川の安泰を図り戦乱の世に戻さないために、天守を起こす決定には変わりありませんでした。しかし、その天守がこれまでにないものに変わることになります。織田・豊臣時代には黒漆と金箔の厳かな造りで、天守そのものが巨大な鎧兜のように敵も味方にも畏怖の念を起こさせるものでした。しかし家康が命じた天守は白壁。天守の壁を白に塗り固めるには大量の漆喰を調達しなければならず、石灰石鉱山の発掘が急務。そこで見出されたのが元々石灰の零細な産地に過ぎなかった東京都青梅市成木でした。大手ゼネコンの最新技術で日本一の採石場となった青梅の地から江戸城に向かう運搬用の道を甲州街道のわき道として切り開きますが、これが現在の青梅街道となりました。その後、城内だけでなく城外の武家屋敷や寺社、日本橋金座、商家の蔵の壁を担当する左官から石灰の需要が高まっていきます。と同時に、街づくりに余念がない秀忠は青梅の森林が林業に適していることに目をつけ、笠取山から青梅を通り江戸湾へ注ぐ多摩川を船で長距離輸送する形をとりました。
わずか半年で完成した天守は五階建て。角材をはめ込み式で組み上げ、釘は一本も使いませんでしたが一本一本がかなり太いので構造上の強度は十分。何より天守全体が純白の白一色。家康が最上階に上り眼下に広がる江戸の街を見下ろした時の胸の内はいかばかりだったか。ボロボロの城とわずかの漁民しかない寒村が一大開発現場となり、江戸は白を基調とした輝くばかりの都市となっていたのです。“関八州には手つかずの未来がある”家康の直感が開いた未来は現在へと繋がっているのです。
(門井慶喜著『家康、江戸を建てる』を参考にしています。)


